1)えてがみってなあに、基本ルール
1.ハガキサイズ(小さい紙)に描くもので、 絵とことばがいっしょにある
2.題材と同じように書かなくていい。うまくなくていい
3.心がこもっていればOK
4.「『へたでいい、へたがいい』っていう言葉があるよ。じょうずじゃなくていいんだよ。」
1.絵手紙とは「絵のある手紙を送ること」としています。
基本は手で書くものです。
はがきに花や野菜など、身近にあるものをかき、相手に伝えたい気持ちを短い言葉で添えます。
2.絵手紙は「みじか主義」
身近なものを絵の題材にして、短い時間でかき、短い言葉を添えて、身近な人に出す。
絵手紙に「失敗」はありません。一生懸命にかいたものは相手の心に必ず届きます。
3.絵手紙のあいことばは「ヘタでいい ヘタがいい」
大切なのは、きれいに整っていることではなく、たとえうまく書けていなくとも、心をこめて全力でかくこと。
その人らしさがにじみ出るような絵手紙は、受け取る相手を喜ばせ元気にします。
これは絵手紙の大事な精神であり、絵手紙の合言葉です。
これは日本絵手紙協会の指針です。
2)どんな道具をつかうのですか?
一番下に、机を汚さないための下敷きとして新聞紙を敷きます。
絵を書くには、主に、学校で使う絵を書く水彩用の道具を使います。
絵を書く道具はたくさんありますが、鉛筆とマーカーで書きましょう。
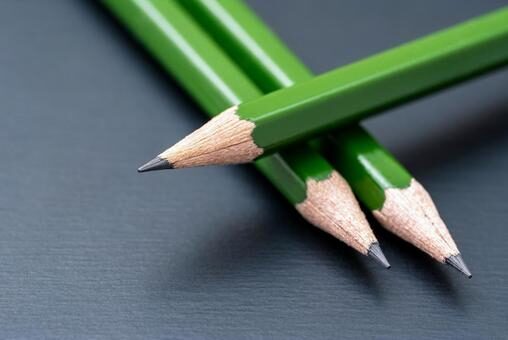
はがきよりも大きい画用紙が書きやすいです。
練習用と本番用を別にして書くと安心です。
練習用の画用紙に鉛筆で下書きして書いてみましょう。
ちょっとまちがったら消しゴムで消してもいいです。
鉛筆で書いたらそその上をマーカーでなぞって、はみ出ないように書きます。
書いたら水彩用の絵の具を使って色をぬると絵が完成します。
あいている所に自分の気持ちをことばで書きましょう。
例えば「○○してくれて、うれしかったよ」でもいいかもしれません。
まずはかいてみよう(創始者小池邦夫の言葉)
形(かたち)を描くのではなく自分の気持ちをかくということ。
形を描こうとすると、たとえばみかんひとつ描くにしても不恰好だとか、みかんに見えないということが気になってくる。
今までは、このような技術にかたよった見方をしすぎていたのではないだろうか。
本当に大事にしなければいけないのは、形ではない。自分のこころ。
自分の心を描くのだと思えば、形はゆがんでいてもかまわない。
展覧会に出すわけでも、ランク付けするというわけでもない。
気心のしれた友だちや知り合いに手紙を出すのだから気楽に考えればいい。
手紙には他人との競争などない。
受け取った相手が少しの間喜んで、楽しい気分になってくれれば、それでいい。
絵手紙にテストはないのだから、自由に、思うままにかこう
4)道具のおき方はどうすればいいですか?
道具の置き方は、右側に絵の具と鉛筆、消しゴム、マーカー。
左には、書くためのハガキか画用紙をおきます。
上の方に、学校で使う水入れと折りたたんだテッシュペーパーをおきます。
注意することは、水をこぼさないことです。
絵の書く題材は左上におくといいでしょう。
参考のための画像を見てください。
5)書くテーマを決める
誰に、どんな絵を書けばいいのでしょうか?
小学生には「身近なもの」をテーマにすると描きやすいです。
えてがみは、だれにどんなことを書いても自由ですが、書こうとする前に考えて決めなければいけません。
書いている途中で、気持ちが変わると、別の画用紙に何枚もかくことになって完成しません。
1.季節のくだもの(いちご、すいか、みかん)花(チューリップ、ひまわり)
2.好きなもの(おもちゃ、ペット)家族や友だちへのメッセージ
書く前に、誰に書くのか、どんな絵を書くのか決まったら、画用紙のうらに、それを書いておきます。
「○○さんに、○○の絵をかきます」と書きましょう。
きょうは、初めてなので、皆さんのお母さんママに書くのはどうでしょうか?
絵の題材をえらぶにも迷ってしまうので、きょうは先生が決めてみました。
「イチゴ」を書いて、お母さんにとどけてみましょう。
イチゴの絵のあいている所に、伝えたいことばを短く書きます。
自分の気持ちをすなおにことばで書きましょう。
例えば「○○してくれて、うれしかったよ」でもいいかもしれません。
絵を書いたら、自分の名前を「左下に小さく」書きましょう。
名前を書いたら、前の方に出しましょう。
6.書き方の手順(ステップで教える)
題材をよく見てみよう➡ 鉛筆でうすく書く➡ 黒いマーカーでなぞる(絵手紙っぽくなる!)
➡ 色をぬる(クレヨンや絵の具) ➡ことばを書く ➡ 名前を書く (これでできあがり)
書き方をもう少し詳しく説明しましょう。
大きく書くというのは、どういうこと?
色はどのようの塗るの?
1)筆に水を付ける➡ 2)筆に絵の具の色を付ける➡ 3)テッシュで確かめる
➡4)画用紙に色を塗る うすい時はもう1度くりかえす
自由に書いていいとは、どういう意味ですか?
手紙といっても「はがき」も手紙です。
「絵が書いている手紙」、言葉が思い当たらない時は、言葉を書かなくても絵手紙です。
絵が書いていないと絵手紙ではないのでしょうか?
いいえ、大きな文字だけ1字書いても絵手紙です。
(この場合、字がアートのように変化に富んでいる場合が多い)
ですが、小さい文字でお知らせの文章を書いたのは絵手紙とはいいません。
絵の題材は何を書いても自由です。
手紙ですので受け取る人に、意味が伝わらないといけません。
受け取る人が絵手紙を見て、送った人の気持ちを理解し、喜んでくれればいいのです。
喜んでくれない場合もあります。また、何日もたってから喜ばれることもあります。
それは、受け取った相手の人が、良く見て、考えて決めることだからです。
書く内容は自由ですが、受け取った人にも自由があり、どのような気持ちで見てくれるかも自由なのです。
絵手紙にはテストも競争もありません。
現在の学校教育では、優劣もあり競争もありますが、絵手紙にはそれはありません。
学校では、先生たちが点数を付けますが、絵手紙では受け取った人が自由に決めます。
受け取る人との信頼関係で「自由に」反応することができます。
受け取った絵手紙を額に入れて飾ったり、いろいろな楽しみ方をしています。
電話や絵手紙で返信をすることもあれば、返信をしない人もいます。
それも、受け取った相手の人の自由です。
返事の絵手紙が欲しいと思うのは、「自分勝手な自由」で、相手の人を困らせることです。
お友だちの絵手紙を見るときに、自分が書いている人の立場で見るでしょうか?
受け取った人の気持ちで見るでしょうか?
1枚の絵手紙から、何を想像しますか?まずは、今日のようにがんばって考えている人の姿を思い浮かべてみましょう。それでは、お友だちが書いたものを見て、どんな気持ちで書いたのか考えてみましょう。
お友だちみんなの絵手紙を見てみましょう
お母さんやお父さんに届ける前に、お友だちみんなの絵手紙を見て、良く書けているところを探して学ぶことができます。
絵手紙を、かいたら、最後に道具を片付けます。
次に良い絵手紙を書くためには、ていねいに片づけることが大事なんですよ。
では、絵手紙の初めての書き方のお話はこれで終わって、実際に書いていきましょう。